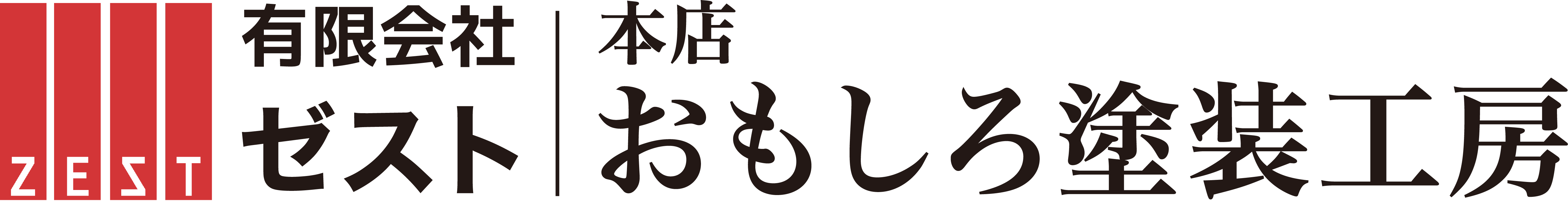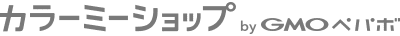変わり塗り 【その他の変わり塗り】
| 蒔き貝研ぎ出し塗り | 渦巻き塗り | 石地塗り | 根来塗り/逆根来塗り ||紅葉塗り | 緑ツイシュ | 茶ツイシュ | その他の変わり塗り |

変わり塗りとは、塗装によって漆などの伝統的な工芸を再現する技術です。 下に挙げた変わり塗りは、全て塗装で表現しています。 実際にこうぼうちょうが作った手板と簡単な工程表を紹介しています。 変わり塗りの絵をクリックしてください。今後少しずつ手板を作り紹介していきます。 リペイントご希望の際に変わり塗りを指定する際には、このページの番号/名前でご指定ください !

1.棕梠毛塗り

2.虫喰い塗り

3.亀甲塗り

4.七子塗り

6.鼈甲塗り

7.カスミ塗り

8.木目描き塗り-1

9.木目描き塗り-2

10.布目塗り

11.木肌塗り

12.大理石塗り

13.木目立て塗り

14.落葉塗り

15.津軽塗り(ボタンシボ)

16.津軽塗り(タタキシボ)

20.黒縞塗り

21.梨地塗り

22.春慶塗り

23.フレークトーン(レッド)

24.キャンディートーン(レッド)

25.キャンディートーン(ゴールド)

26.金砂塗り-1

27.金砂塗り-2

28.雪花塗り

31.曙塗り

32.鎌倉塗り

34.チラシ塗り
-
【パターンの解説】
4.「七子」とは魚の卵のことで、「魚子」「斜子」とも書きます。
魚卵の小さな粒が一面に並んだような柄で、織物や彫金にも用いられています。
津軽地方の漆器に塗られてきました。
10. 京都の塗り物に多く用いられてきました。
15.呼び名どうり津軽弘前産の塗り物に用いられる、というよりも津軽漆器の代名詞ともなっています。
16.木曽漆器にも同様手法のものがあり、堆朱(ついしゅ)塗りとも呼ばれています。
24.25. Web上ではシルバーの光沢を表現できません。見本は粒粒が光っているものとお考えください。
29. 和歌山県岩出町根来にある真義真言宗総本山:大伝法院(一名根来寺)の僧侶が中世に 日用した漆器に端を発するもの、といわれています。
31. 金沢漆器に多用されています。
32.鎌倉時代に仏師康運が仏具を作ったのに始まるといわれる鎌倉彫りの仕上げには 欠かせない漆塗り技法です。 -
■ご注文の際の注意点
現在お選びいただける変わり塗りは以下の通りです。
しゅろげ塗り・虫食い塗り・木目描き塗り・布目塗り・木肌塗り・津軽塗り・津軽塗りタタキシボ・梨地塗り・春慶塗り・渦潮塗りA・渦潮塗りB・石地塗り・根来塗り・逆根来塗り・曙塗り・紅葉塗り