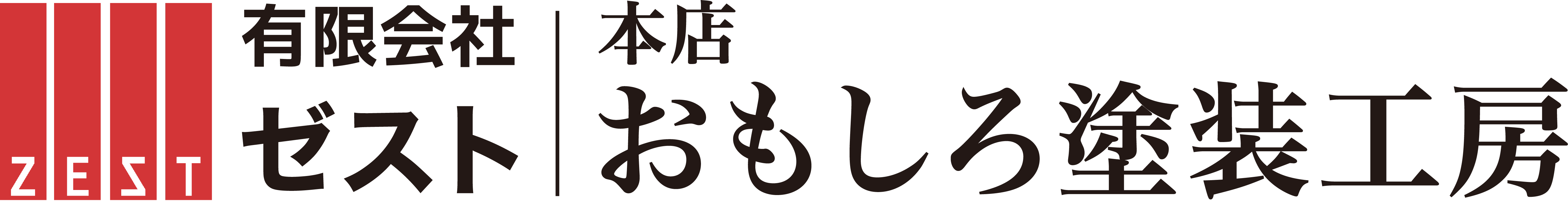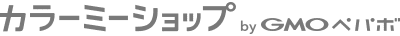REPAINT傷ついたスピーカー(補色修正)塗装
おもしろ塗装工房は各種製品のリペイント・再塗装を承ります。お申込みはこちらから
※電話でのリペイント見積もり依頼は、受け付けておりません。
お客様の要望
震災で傷ついたスピーカーを直したい。-
本日の塗装屋ドットコム 2011/5/19
Speaker01
小さなキズがたくさん各所に見られます。
完璧には直せませんが出来る限り
対応してみます。
乞うご期待! -
本日の塗装屋ドットコム 2011/5/22
Speaker02
1
2
そして最初にパテで、傷を埋めずに、下地が出てしまっている、白の部分を同色で補色していきます。
写真1
同じように、傷のある場所を補色していきます。
写真2
補色はウレタンサンディングの中にステインを混ぜています。
ステインはマホガ二・ブラウンを混ぜています。 -
本日の塗装屋ドットコム 2011/5/24
Speaker03
1
2
3
そして、パテ埋め・・・
とはいっても今回はポリサンを盛っています。
写真2
ポリサンは透明度が高く、樹脂分が多いため
一度に盛ることができるからです。
写真2
一般の方が挑戦するなら、ウレタンサンディングでも代用できます。
しっかりとピン角を出し、目痩せがあるので、たっぷり目に盛るのが基本となります。
ウレタンサンディングの場合は目痩せがあるので
2回〜3回ぐらいに分けて盛るのがよいでしょう。
-
本日の塗装屋ドットコム 2011/6/2
Speaker04
1
2
3
4
平らになったところで、密着を良くするために
#1000で軽く足付けをします。
その後、チリ・ほこりを払います。
写真1
そしてウレタンサンディング吹き
2(主液):1(硬化剤):1(薄め液)
の混合比であっさり目で吹いています。
写真23
今回全体にウレタンサンディングを吹くのですが、
これにはちゃんとした理由があり、
ポリサンを 平らにしたのち、直接ウレタンフラットを吹くと、パテ埋めした箇所 とそうでない場所との境の差が仕上がった後にわかってしまうため、
ポリサンが平らになったところで、
一度全体的にウレタンサンディングを吹いて境をわからなくするために行っている作業なのです。
わかるかな〜
ま〜そんな意味なのですよ!
話を元に戻して・・・
そして、上の向きになっている部分のみをサンディング吹いているので、前面・側面2面・裏面・天板と5回に分けて、塗っては乾燥させて側面吹き、裏面吹き・・・・
作業を繰り返します
写真3は裏面・写真4は表面を吹いています。
乾燥時間もあるので各1面を吹いて終了し乾燥させて・・・
サンディング作業だけで5日は掛かってしまいました。
-
本日の塗装屋ドットコム 2011/6/21
Speaker05
1
2
3使用スプレーガン 明治FM2−G05平吹き
作業は進めております。
今日はウレタンサンディングの研磨です。
仕上げ前の作業なので、慎重に作業を進めます。
まずはベルトサンダー#600で回転をスローに落とし
ゆっくり丁寧に研磨していきます。
写真1
側面・裏面・表面・天板と1台で5面をベルトサンダーで研磨していきます。
写真 2一台完成です。
この作業は仕上げたときの表面凸凹をなくす役割があります。
ベルトサンダーで仕上げた塗装の仕上がりは表面が綺麗なのです。
ベルトサンダーがない方は、ミニサンダーでも対応できます。
そしてウレタンフラット吹きです。
今回見本のスピーカーがウレタンフラットの全消しの艶にぴったりだったので、全消しを選択しました。
作った量は主液200ml
4:1:2の混合比で作ったため
主液200ml:硬化剤50ml:薄め液100mlの配合になり
混合合計量350mlとなりました。
これだけあれば、2本吹くのに、ちょっとあまるかな?
あっそうそう、薄め液も重要な要素です。
今回 薄め液は乾燥の遅い夏用を使用、乾燥の速いタイプにすると、
乾燥が早すぎて、最初に吹いた部分に、塗料ミストが付着し塗膜表面がザラつくからです。
吹き方は、チリ払いをした後、一番目立たない裏面から一気に吹いていきます。
一台を2分以内で吹きたいですね!
裏面→側面2面→前面→天板
以上の順番で吹いて行きます。
これは、最初に一番目立たない部分からを吹くことによって、
塗装ミス、艶ムラや、ほこり防止、塗料ミスト付着防止などを防ぐ意味があります。
最初に吹く場所って意外と失敗しやすいんです。
だから失敗しても良い場所から吹くんです。
また最初に立面を吹くことによって、ほこりが乗りづらく、最後にほこりの乗りやすい天板を吹いて終了とします。
写真3
完成間近!